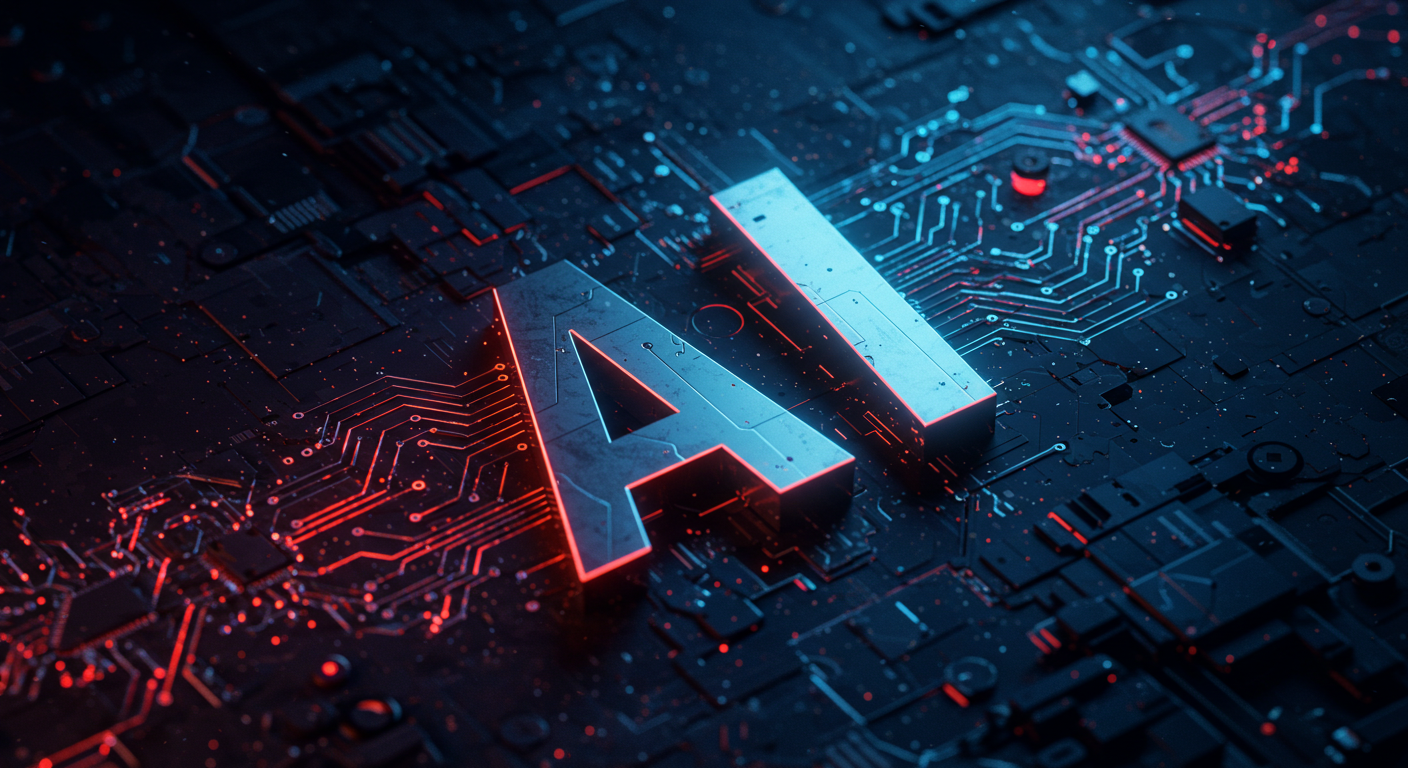企業のためのAI導入完全ガイド|汎用業務から業界別事例まで徹底解説
「AI導入したいけど、どうやって進めればいいの?」 「どの事業者と組めばいいんだろう...」
このように、AI導入にお悩みではないでしょうか?
昨今、先進国ではAI(人工知能)の活用が各産業で加速している一方、日本企業、特に中小企業においては、依然としてアナログな業務プロセスやレガシーシステムが根強く残り、世界平均に比べてAI導入が後手に回っている現状があります。
AIを導入するためには正しい導入プロセスを理解することが不可欠です。
この記事ではAI導入の進め方とそれぞれのステップにおけるポイントを実例を交えて解説します。
また、弊社ではマッキンゼーやGAFA出身のAIエキスパートがAI導入に関する無料相談を承っております。
無料相談は先着20社様限定で「貴社のAI活用余地分析レポート」を無償でご提供するキャンペーンも実施中です。
ご興味をお持ちの方は、以下のリンクよりご連絡ください:
AI導入に関する無料相談はこちら
資料請求はこちら

AI導入.comを提供する株式会社FirstShift 代表取締役。トロント大学コンピューターサイエンス学科卒業。株式会社ANIFTYを創業後、世界初のブロックチェーンサービスを開発し、東証プライム上場企業に売却。その後、マッキンゼー・アンド・カンパニーにコンサルタントとして入社。マッキンゼー日本オフィス初の生成AIプロジェクトに従事後、株式会社FirstShiftを創業。
企業におけるAI導入の意義・メリット

AI導入は企業の競争力強化や新たな価値創造に大きく貢献します。世界経済全体および各企業の経営に莫大な効果をもたらすと推計されています。
ここではAI導入すべき4つの理由を解説します。
競争力の強化
AIは大量データの高速解析により、市場動向や顧客ニーズを素早く把握し、ビジネス競争力を向上させます。AIが提供する分析結果を活用することで、製品やサービスの開発スピードを加速させることができます。
また、24時間稼働するAIによってリアルタイムな監視や予知保全が可能となり、製品やサービスの品質向上に直接寄与します。これにより顧客満足度の向上とリピート率の増加が期待できます。
新たな価値創造
AIの導入により、従来は気づかなかった潜在的な顧客層やサービスアイデアを発掘できます。膨大なデータから見出されるパターンや相関関係は、人間の分析だけでは見つけられない新たな視点を提供します。
これにより革新的なビジネスモデルが生まれ、自社の収益源や成長機会を大幅に拡大させることが可能になります。特に既存事業の延長線上ではない、まったく新しい価値提案につながるケースも増えています。
意思決定の高度化
AIが提供する定量的な分析や予測モデルを活用することで、より正確かつ迅速な経営判断が可能になります。従来は経験や勘に頼っていた部分を、データに基づく客観的な意思決定に置き換えられます。
経営戦略やリスク管理など重要な判断においてAIの分析結果を参照することで、組織全体の意思決定プロセスが効率化し、業績向上につながります。特に不確実性の高い状況での判断精度が向上する点は大きなメリットです。
将来リスクへの備え
AIの早期導入は将来的なビジネスリスクを軽減する効果があります。レガシーシステムの更改が進まないことでサイバーセキュリティ対策が不十分になったり、社内IT人材が不足したりすることは企業存続に関わる問題です。
また、2040年問題に伴う労働力不足や社会保障費増大のリスクもあります。これらを回避するためにも、早期のAI導入による業務効率化と自動化が求められています。
日本企業のAI導入状況

日本企業のAI導入率は世界的に見て低水準にとどまっています。総務省の「令和元年版情報通信白書」などの各種報告によると、日本のAI活用企業、いわゆる「AIアクティブ・プレイヤー」の割合は、主要国と比較して著しく低い状況です。
国際比較では、中国企業の導入率が85%に対し、日本は約39%と大きな差が存在します。この差は年々広がる傾向にあり、日本企業の競争力低下が懸念されています。
業種別にみると、テクノロジー・メディア・通信分野では海外と同等の水準にあるものの、エネルギーやヘルスケアなど多くの産業分野では導入が著しく遅れています。特に中小企業におけるAI活用の遅れは深刻で、デジタル格差の拡大が進んでいます。
AI導入の5つのステップ

AI導入は「調査・情報収集」から始まり、段階的に進めていく必要があります。ここでは、成功するAI導入に必要な5つのステップとそれぞれのポイントを解説します。
1. 調査・情報収集
最初のステップでは自社の課題を正確に把握し、AI適用の可能性を探ります。自社の業務プロセスを詳細に分析し、どの部分がボトルネックとなっているか、AIによって改善できそうな領域はどこかを特定します。
また同業他社のAI導入事例を調査することで、業界特有の課題解決方法やベストプラクティスを学ぶことができます。この段階では幅広い情報収集を行い、AI導入の方向性を定めるための基礎を固めることが重要です。
2. 目的設定
AI導入の具体的な目的と達成したい成果を明確に定義します。この段階では以下の2つのポイントが重要です。
- 現状分析と課題抽出: 自社の業務プロセスを細かく見直し、どの部分がボトルネックとなっているかを洗い出します。課題の優先順位付けを行い、AIによって最も効果的に解決できる領域を特定します。
- 導入目的の明確化: 業務効率化、コスト削減、売上向上など、AI導入によって達成したい目標を数値目標と共に設定します。「〇〇の業務時間を△△%削減する」といった具体的な指標を設定することで、後の効果測定がしやすくなります。
明確な目標設定はプロジェクト全体の方向性を定め、関係者間での認識共有にも役立ちます。
3. 開発パートナーの選定
適切な開発パートナーを選ぶことはAI導入成功の鍵となります。ほとんどの企業では社内にAI開発の十分なケイパビリティを持っていないため、外部の専門家や開発ベンダーとの連携が不可欠です。
専門家との連携においては、単なる技術力だけでなく、自社の業界や事業に対する理解度、過去の類似プロジェクトの実績、コミュニケーション能力なども重視すべきです。複数の候補から比較検討し、目的に最適なパートナーを選定しましょう。
また、パートナー選定時には将来的な保守運用体制についても確認しておくことが重要です。
4. 構築
AI導入の実際の開発・構築フェーズでは、適切なツール選定とデータ準備が重要です。この段階では以下の点に注意して進めます。
- 適切なツールの選定: 業種・業態に応じた機能を持つAIツールを比較検討し、必要十分な機能を備えたものを選びます。過剰な機能を持つツールは導入コストが高くなる傾向があるため、自社のニーズに合ったものを選定することが重要です。
- AI学習用データの整備: 大量のデータを整え、AIが効率的に学習できる状態にデータをクレンジング・整形します。データの品質はAIの精度に直結するため、この工程は特に丁寧に行う必要があります。
開発途中での進捗確認や方向性の修正も重要です。定期的なレビューミーティングを設け、当初の目的から外れていないか確認しながら進めましょう。
5. 運用
開発したAIシステムを本格運用する前に、試験運用とフィードバックサイクルを確立します。この段階での主なポイントは以下の通りです。
- パイロットプロジェクト: 限定された部門や業務で試験運用を開始し、システムの動作や業務への影響を検証します。小規模から始めることで、問題が発生した場合のリスクを最小限に抑えられます。
- フィードバックによる改善: 試験運用で得た結果をもとに、システムや運用体制を改善し、段階的に全社展開へと移行します。利用者からのフィードバックを積極的に収集し、継続的な改善に活かすプロセスを確立することが重要です。
運用段階では担当者の育成も並行して行い、社内でのAI活用ノウハウを蓄積していくことが長期的な成功につながります。
AI導入が見込める業務内容

AIは様々な業務領域に適用でき、特に定型的で繰り返し行われる作業において高い効果を発揮します。ここでは、業種や企業規模を問わず共通して存在する業務領域でのAI活用について紹介します。
データ分析・予測
AIはビッグデータから有意義なパターンを発見し、将来予測を行うことに優れています。マーケティング部門での顧客行動分析や、財務部門での売上予測、在庫管理部門での需要予測など、様々な業務で活用できます。
例えば、小売業では過去の販売データと天候や季節などの外部要因を組み合わせて需要を予測し、適切な在庫管理を実現できます。また、製造業では機械の異常を事前に検知する予知保全にも応用されています。
実際に、セブン銀行はAI技術を用いてATM運用の効率化を行い、入出金差額予測モデルを構築して作業効率化を実現しています。
顧客対応・サポート
AIチャットボットや音声アシスタントによる顧客対応の自動化は、人的リソースの効率化と24時間対応の実現に貢献します。FAQへの回答や簡単な問い合わせ対応、予約受付などを自動化することで、人間のオペレーターはより複雑な案件に集中できるようになります。
また、AIによる感情分析技術を活用すれば、顧客の感情や意図を理解し、適切な対応を行うことも可能になります。
例えば、共栄火災海上保険はAIチャットボット「WisTalk」を導入し、定型的な問い合わせへの自動化や即時的な回答提供を実現し、月間平均9100件の利用という成果を上げています。
文書作成・処理
AI技術を用いた自然言語処理は、文書の作成、要約、翻訳などの業務を大幅に効率化します。会議議事録の自動作成や契約書のチェック、メールの下書き作成など、様々な文書業務に活用できます。
また、OCR(光学文字認識)技術と組み合わせることで、紙の書類のデジタル化も効率的に行えるようになります。
三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)では独自開発のSMBC-GAIと名付けられたAIアシスタントツールを開発し、文章作成、要約、翻訳などの業務自動化による生産性向上を実現しています。
バックオフィス業務の自動化
総務、経理、人事などのバックオフィス業務には定型的な処理が多く、AI導入による効率化の効果が高い領域です。経費精算、給与計算、勤怠管理など、ルールベースの業務を自動化することで、ヒューマンエラーの削減と処理時間の短縮を同時に実現できます。
特に請求書処理や仕訳入力などの会計業務は、AI-OCR技術との組み合わせにより大幅な効率化が可能です。多くの企業では経理担当者の作業負担軽減と精度向上に成功しています。
freeeやマネーフォワードなどが提供するクラウド会計ソフトは、AIによる自動仕訳機能を搭載し、中小企業のバックオフィス業務効率化に貢献しています。
社内ナレッジマネジメント
AI技術は社内に蓄積された情報やノウハウの管理・検索・共有を効率化します。社内文書や過去のプロジェクト情報、FAQなどを一元管理し、必要な情報に素早くアクセスできる環境を構築することで、業務効率の向上と意思決定の迅速化につながります。
AIによる自然言語理解を活用することで、従来のキーワード検索では見つけられなかった関連情報も抽出できるようになり、情報の有効活用が進みます。
コニカミノルタは社内向けAIチャットボット「AIさくらさん」を導入し、業務マニュアルや社内規定などを瞬時に検索・回答できるシステムを構築し、社員の業務効率向上を実現しています。
採用・人事管理
AIを活用した採用プロセスの効率化や従業員管理は、人事部門の業務改善に効果的です。応募者のスクリーニングや適性評価、社内人材の適材適所の配置、従業員の離職リスク予測など、データに基づいた人材管理が可能になります。
また、従業員からの問い合わせに対するAIチャットボットの導入も、人事部門の負担軽減に貢献します。
三井住友信託銀行ではAIを活用した360度評価ツール「GROW360」を利用し、従業員一人ひとりの適性評価とキャリア自律の促進を実現しています。
会議・コミュニケーション効率化
AIを活用した会議の自動議事録作成や要約、多言語翻訳などは、企業内コミュニケーションの効率化に貢献します。リモートワークが普及する中、オンライン会議の内容を自動的に文字起こしし、重要なポイントを抽出するAIツールの需要が高まっています。
また、社内チャットツールにAIアシスタントを導入することで、情報検索やタスク管理の効率化も実現できます。
Microsoftは会議ツール「Teams」にAI機能を統合し、会議の自動文字起こしや要約、多言語リアルタイム翻訳などの機能を提供し、グローバル企業のコミュニケーション効率化を支援しています。
AIの導入事例【業界別】

様々な業界でAI導入が進んでおり、それぞれ特徴的な成功事例が生まれています。ここでは、代表的な業界ごとにAIの導入事例を紹介します。
製造業
製造業では品質管理や設備保全にAIが活用されています。
トヨタ自動車では、工場内のセンサーデータをもとに機械の故障予測を行い、保守の自動化と生産効率向上を実現しています。AIが分析する数万を超えるセンサーデータにより、製造ラインの異常を早期発見し、ダウンタイムの削減に成功しています。
大林組は、SRIインターナショナルと共同で設計初期段階の作業を効率化するAI技術「AiCorb®」を開発しました。複数のデザインを学習し、スケッチや3Dモデルから即座にファサードデザインを生成することで、設計フェーズの時間短縮と効率化を実現しています。
また、鹿島建設は固定カメラと画像AIを利用して建設現場の作業人数や作業時間を自動で分析・可視化するシステムを開発し、手作業での歩掛り調査の労力を大幅に削減しています。このシステムは正確なデータ収集を可能にし、作業の効率と安全性の向上に貢献しています。
医療・ヘルスケア
医療分野ではAIによる画像診断支援や事務処理の自動化が進んでいます。
エムスリーは機械学習技術を活用して、CT画像やMRI画像などの医療画像から病変を高精度で検出するAIシステムを開発しています。このシステムにより、医師の診断精度の向上と診断時間の短縮を両立し、早期発見率の向上に寄与しています。
メドメインは病理診断のデジタル化とAI支援を行う「PidPort」を提供しており、病理医の負担軽減と診断精度の向上を実現しています。AI技術により、がん細胞の検出や分類を自動化し、診断の効率化を推進しています。
また、アルムは医療現場のコミュニケーションプラットフォーム「Join」を開発し、医療画像の共有と診断支援にAIを活用しています。緊急時の迅速な情報共有と意思決定をサポートし、救急医療の質の向上に貢献しています。
小売業
小売業では在庫管理と顧客対応にAIが活用されています。
ユニクロは販売履歴や顧客データをもとにAIが在庫数や商品補充を最適化するシステムを導入しています。需要予測の精度向上により、欠品防止と在庫効率化を実現し、特に季節性の高い商品の在庫管理で大きな効果を上げています。
楽天はパーソナライズド・レコメンデーションシステムを導入し、顧客の購買履歴や閲覧行動を分析して最適な商品を提案しています。AIが顧客の嗜好を学習することで、コンバージョン率の向上と顧客満足度の向上を達成しています。
また、セブン-イレブンは「7DREAM」プロジェクトでAIを活用した需要予測と発注自動化システムを展開し、各店舗の特性に合わせた最適な在庫管理を実現。食品ロス削減と売上向上を同時に達成しています。
金融業
金融業では不正検知とリスク管理にAIが積極的に導入されています。
大和証券は全社員約9,000人を対象にChatGPTの利用を開始し、英語等での情報収集サポートや資料作成の効率化を実現しています。これにより、顧客と接する時間や企画立案など、本来業務に充てる時間創出を可能にしています。
三菱UFJ銀行は従業員向けにMUFG版「ChatGPT」を提供し、稟議書の作成アシストや金融レポートの要約、行内手続き照会などの業務で活用しています。既に110以上の業務で使用され、業務効率の大幅な向上を実現しています。
また、みずほフィナンシャルグループは事務手続照会や与信稟議作成の時間短縮と高品質化を実現するためテキスト生成AIを導入しました。これにより稟議作成にかかる時間が大幅に削減され、高度な業務に人的リソースを集中できるようになっています。
建設・不動産
建設業では画像認識AIによる品質検査や安全管理が注目されています。清水建設は全従業員向けに生成AIサービス「法人GAI」を提供開始し、文書作成やデータ分析、プロジェクト管理など様々な業務をサポートしています。これにより業務効率の向上と品質改善を実現し、従業員はより創造的な業務に集中できるようになっています。
大和ハウスはAIヘルプデスクをMicrosoft Teams上に導入し、18,000人の従業員の問合せを一元化しました。対話データをナレッジ化し、チャットボットが即座に回答する仕組みを構築することで、問合せ対応の効率向上と業務改善を推進しています。
また、LIFULLは不動産業界で初となる生成AIを活用した一般ユーザー向けサービスを提供し、野村不動産ソリューションズと共同でAI ANSWER Plusを開発しました。不動産に関する質問への回答や条件に基づいた物件紹介により、顧客体験の向上を実現しています。
下記の記事では、AIの中でも急成長している生成AIの活用事例や企業への導入方法を業界別に紹介しています。ぜひご覧ください。
AIを導入する際の注意点

AI導入には様々なメリットがある一方で、考慮すべき課題やリスクも存在します。ここでは主な注意点を解説します。
初期投資
AI導入には相応の初期投資が必要です。インフラ構築費やライセンス料など多額の費用が発生するため、投資目的と費用対効果を明確化することが重要です。
投資回収期間を具体的に設定し、段階的な導入計画を立てることで、リスクを抑えながら進められます。また、クラウドサービスの活用など、初期投資を抑える方法も検討すべきでしょう。
運用上の課題
AIは導入して終わりではなく、継続的な運用・保守が必要です。AIは定期的なモデル再学習やデータ品質の維持が必要であり、これらを怠ると性能が低下していきます。
運用コストや担当人材の確保に加え、現場との連携体制を整えなければ、長期的な成果を得ることは難しいでしょう。運用体制を事前に計画し、必要なリソースを確保しておくことが重要です。
従業員のスキルギャップ
AI活用には特定のスキルが必要であり、従業員間でスキルギャップが生じやすい課題があります。高度な分析能力やプログラミング知識が求められるため、現場社員との能力差が問題になることがあります。
この課題に対しては、教育プログラムや研修を整備し、段階的なスキル習得を支援する取り組みが必要です。また、AIリテラシーの底上げを組織全体で行うことも重要です。
セキュリティリスク
AIは大量の機密データを扱うため、セキュリティ対策が不可欠です。不正アクセスや情報漏洩のリスクが高まるため、適切な対策を講じる必要があります。
アクセス権限の厳格化や通信の暗号化などのセキュリティ対策を徹底し、データ保護のルールを明確化することが重要です。また、定期的なセキュリティ監査を実施し、脆弱性を早期に発見・対処する体制も必要です。
まとめと今後の展望
AI導入は企業の競争力強化と業務効率化に大きく貢献する重要な取り組みです。本記事では、国内外のAI導入状況を背景に、日本企業が直面する課題とAI導入の進め方について解説しました。
AI導入のプロセスは「調査・情報収集」「目的設定」「開発パートナー選定」「構築」「運用」の5ステップで進めることが重要です。それぞれのステップで適切な取り組みを行い、課題を克服することで、成功へと導くことができます。
今後、技術の進化とともにAI活用の幅はさらに広がることが予想されます。中小企業においても柔軟かつ迅速な対応が求められる中、自社の強みや業務プロセスを見極め、戦略的なAI導入を進めることが、企業の未来を切り拓く鍵となるでしょう。